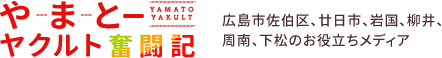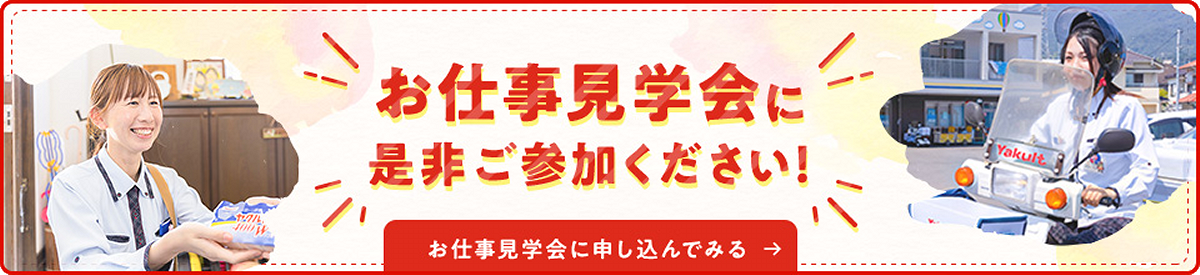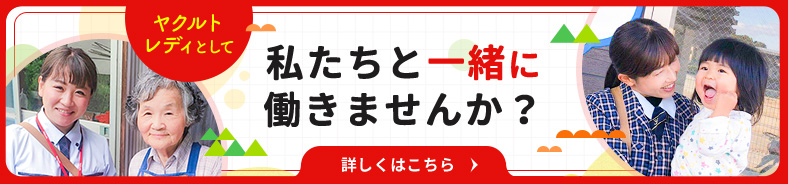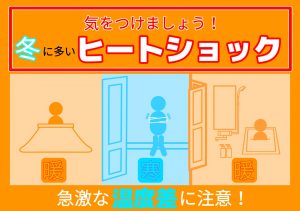こんにちは!やまとーヤクルトの梅本です。
本格的な夏が到来しました!7月下旬から8月上旬は、一年で最も暑さが厳しくなる時期です。
夏バテや熱中症に負けず、毎日を元気に過ごすための健康情報をまとめてみました。この時期に悩まされがちな寒暖差アレルギーの対策も、併せてご紹介します。
1. 徹底したい熱中症対策!知っておきたい具体的な症状と応急処置
この時期、最も気をつけたいのが熱中症です。最悪の場合、命に関わることもあるため、正しい知識を持つことが重要です。
熱中症のサインを見逃さないで!
熱中症は、段階的に症状が進行します。初期症状を見逃さず、早めに対処することが大切です。
- 軽度(熱失神・熱けいれん)
- めまい、立ちくらみ、一時的な意識消失
- 筋肉のこむら返り、手足のしびれ
- 大量の発汗
- 気分が悪い、だるい
- 中度(熱疲労)
- 頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感
- 体がぐったりする
- 集中力や判断力の低下
- 体温が37〜39℃程度に上昇
- 重度(熱射病)
- 意識がない、呼びかけに反応しない
- けいれん、手足のつっぱり
- 体温が40℃以上に上昇し、触ると非常に熱い
- 汗をかいていないのに皮膚が乾燥している(重度の場合は発汗が止まることがあります)
熱中症かな?と思ったら、すぐに行動を!
「もしかして熱中症かも?」と感じたら、以下の応急処置をすぐに実践しましょう。
- 涼しい場所へ移動する: エアコンが効いた室内や、風通しの良い日陰に移動させましょう。
- 体を冷やす:
- 衣服をゆるめて風通しを良くします。
- 首筋、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている場所を冷たいペットボトルや氷のう、濡らしたタオルなどで集中的に冷やします。
- 意識があれば、体に水をかけたり、濡らしたタオルで体を拭いて、うちわや扇風機で風を当てて気化熱で冷やすのも効果的です。
- 水分・塩分を補給する:
- 意識がはっきりしていれば、スポーツドリンクや経口補水液を少量ずつこまめに飲ませましょう。
- 意識がない場合や、自力で飲めない場合は、無理に飲ませると誤嚥の危険があるため、すぐに救急車を呼びましょう。
- 医療機関へ: 症状が改善しない場合や、意識がない、けいれんを起こしているなど重度の場合は、ためらわずに救急車を呼びましょう。
2. 夏バテに負けない食事のポイント:手軽に作れるおすすめレシピ
食欲が落ちやすい夏ですが、バランスの取れた食事で体力を維持することが大切です。夏バテ予防に効果的な食材と、手軽に作れるレシピ例をご紹介します。
夏バテ対策の食材選び
- ビタミンB1: 糖質をエネルギーに変える手助けをし、疲労回復に役立ちます。豚肉、うなぎ、大豆製品などに豊富です。
- クエン酸: 疲労物質の分解を促進し、食欲増進効果も期待できます。レモン、梅干し、お酢などに含まれます。
- カリウム: 体内の余分なナトリウムを排出し、むくみやだるさの改善に役立ちます。きゅうり、トマト、なす、スイカなどの夏野菜・果物に豊富です。
- たんぱく質: 筋肉や体の組織を作る上で不可欠な栄養素。肉、魚、卵、豆腐などをバランス良く摂りましょう。
手軽でおすすめ!夏バテ対策レシピ例
きゅうりと鶏むね肉の梅和え
【材料(2人前)】
- 鶏むね肉:1枚(約200g)
- きゅうり:2本
- 梅干し:2〜3個(塩分控えめがおすすめ)
- ポン酢:大さじ2
- ごま油:小さじ1
- 白ごま:適量
- 作り方: 鶏むね肉は茹でて裂き、きゅうりはたたいて一口大に。梅干しは種を取って叩き、ポン酢、ごま油と混ぜ合わせる。全てを和えて白ごまを振れば完成です。
- ポイント: 鶏むね肉でたんぱく質を、きゅうりでカリウムと水分を、梅干しでクエン酸と塩分を補給できます。さっぱりとして食欲がない時でも食べやすい一品です。
夏野菜たっぷり!冷たい味噌汁
【材料(2人前)】
- なす:1/2本
- きゅうり:1/2本
- オクラ:3本
- ミョウガ:1個
- だし汁:400ml
- 味噌:大さじ2
- 作り方: なすときゅうりは薄切り、オクラは小口切りに。だし汁で野菜をさっと煮て冷まし、味噌を溶き入れる。仕上げに刻んだミョウガを乗せれば完成です。
- ポイント: 火を使わずに作れるので暑い日にもぴったり。夏野菜のカリウムや食物繊維、味噌の発酵食品としての栄養素を効率良く摂れます。
3. 質の良い睡眠で疲労回復!寝苦しい夜の快眠術
快適な寝室環境を作る
- 室温・湿度の調整: エアコンは26〜28℃を目安に、除湿機能も活用して湿度は50〜60%に保つと快適です。タイマー機能を活用し、寝入りばなの数時間だけでもつけておくのがおすすめです。
- 寝具の選び方: 吸湿性、速乾性に優れた接触冷感素材のシーツやパジャマを選ぶと、汗をかいてもべたつきにくく、快適に眠れます。
- 遮光・遮音: 強い日差しや外部の騒音は睡眠の妨げになります。厚手のカーテンなどを活用しましょう。
就寝前のリラックス習慣
- ぬるめの入浴: 就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かると、体温がほどよく上がり、その後下がることで自然な眠気を誘います。
- 軽いストレッチ: 血行を促進し、心身の緊張をほぐします。激しい運動はかえって交感神経を刺激してしまうので避けましょう。
- リラックスできる飲み物: ホットミルクやカフェインを含まないハーブティーなど、体を温めてくれる飲み物がおすすめです。
4. 冷房病(クーラー病)と寒暖差アレルギーにも注意!具体的な症状と対策
室内と屋外の温度差が大きいと、自律神経のバランスが乱れて冷房病(クーラー病)や寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)を引き起こすことがあります。
冷房病の主な症状
- 全身の倦怠感、だるさ
- 頭痛、肩こり、腰痛
- 手足の冷え、むくみ
- 食欲不振、下痢、便秘
- 自律神経の乱れによる精神的な不調(イライラ、不眠など)
寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)とは?
特定の物質に反応するアレルギーとは異なり、急激な温度変化が刺激となって、鼻の粘膜の血管が拡張・収縮する際に起こる症状です。
- 主な症状: くしゃみ、鼻水(透明でサラサラ)、鼻づまり。花粉症やハウスダストアレルギーと似ていますが、目のかゆみはほとんどありません。
冷房病と寒暖差アレルギーの予防と対策
これらの症状は、自律神経の乱れが大きく関わっています。以下の対策で、体への負担を減らしましょう。
- 服装で体温調節を:
- 冷房が効きすぎている場所では、カーディガンや薄手のジャケット、ストールなどを用意して体を冷やしすぎないようにしましょう。
- 特に首元、お腹、足首など「首」とつく部分は、太い血管が通っていて冷えやすいので、温めることを意識してください。
- 体を冷やさない工夫:
- 冷たい飲み物ばかりでなく、常温の水や温かいお茶、白湯を意識的に摂るようにしましょう。
- シャワーだけでなく、湯船に浸かることで体を芯から温め、冷房で冷え切った体をリセットできます。ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。
- 自律神経を整える:
- 規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠とバランスの取れた食事を摂りましょう。
- 軽い運動(ウォーキングやストレッチなど)で血行を促進し、自律神経の働きを整えましょう。
- ストレスをため込まないよう、趣味の時間を作るなどリラックスできる時間を作りましょう。
- 食事で体を温める:
- ショウガ、ネギ、ニンニク、トウガラシなど、体を温める効果のある食材を積極的に食事に取り入れましょう。
まとめ
7月下旬から8月上旬は、健康トラブルが起こりやすい時期です。
こまめな水分補給、バランスの取れた食事、質の良い睡眠で体力を維持しましょう。また、冷房対策として服装や飲食物に気を配り、自律神経を整えることも大切です。
無理をせず、自分の体の声に耳を傾け、必要であれば専門医にご相談くださいね!